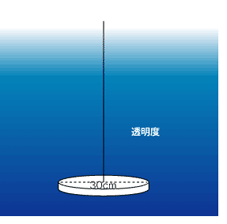 海は青くて美しい、といっても、いつもいつも水が透明で、龍宮城のような海中景観を楽しめるとは限りません。河口に近い海域や外洋水との入れ替わりが少ない湾内などは濁っていますし、大雨が降って茶色く染まった川の水が流れこんだり、台風のすぐあと海底の砂が舞い上がってまだ沈降していなかったり、赤潮が発生したりすると海は濁ります。海の濁りは、海岸地形や天候や季節の影響を受けます。
生活産業排泄物、砂泥、プランクトンなどさまざまな浮遊物が、水を濁らせ視界をさえぎります。浮遊物の密度が増すにつれて、どんどん視界が悪くなります。濁りがひどいところでは、光が散乱して明るさがあっても少し離れたところも見えない状態になり、濁らせる浮遊物が黒色系なら光を吸収し反射光の光量も減るので暗い水中となります。
スノーケリングやダイビングを楽しむ者にとっては、水の濁りがいちばん切実なものです。水の清濁を示すのに透明度と透視度があります。
【透明度:m】
水面から垂直方向の見え方で、正確な測定方法は30㎝の白色の円板を水中に降ろし、肉眼で白板が見えなくなる深さをいいます。この深さは、透明度板からの反射光とその上にある海水からの散乱光との相対的な強弱により決まるため、空の晴れや曇り、明るさにはほとんど関係しません。
スノーケリングやダイビングでは、こうした測定はいちいちできないので、その人の見え方の基準で示している場合が多いので、透明度は人によってまちまちです。ちなみに、黒潮域の透明度は30〜40m、親潮域で10〜15mで、測定された最高値はサルガッソー海の66.5m
だそうです。
【透視度:m】
水平方向の見え方を示すのに使います。同じ濁度であっても、深度と光量によって大きく変化します。透明度がなくても、水中に潜り水平方向を見ると、思ったより明るく透視のきく景観に出会うときもあります。水の透視度は一般には使われることなく、ダイバー特有の指標です。
|